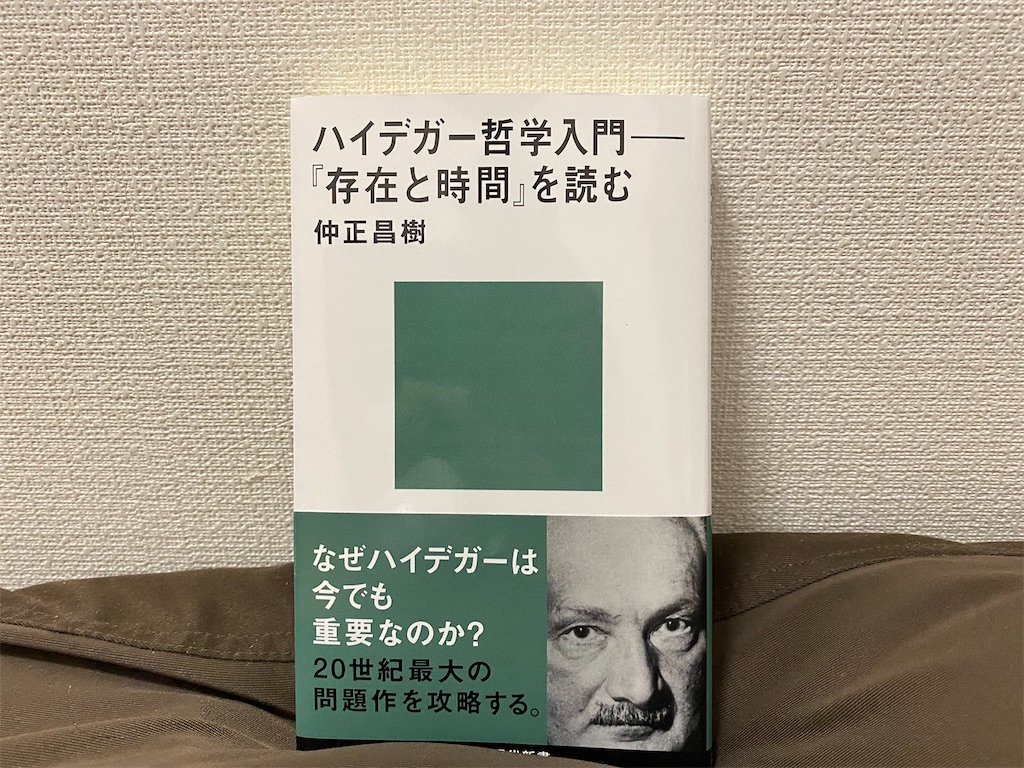
書籍「ハイデガー哲学入門ー『時間と存在』を読む」を読みました。
今回この書籍を選んだきっかけは、前回読んだ書籍「シンギュラリティは近い」の中でAIが自分たちにも意識があると主張するようになった時にどう折り合いをつけていくのかという問題は、もはや科学で解決できる範疇を超えていて哲学の存在論にアプローチする必要があるとあったことで、その存在論を覗いてみようと思ったからです。
しかし読んでみたとはいうものの熟読はせずざっと読んだという感じ。というのも、熟読するにはまだ私の関心が浅かったことや深く理解するにはかなり読み込まなければならなかったこと、そして本文中に以下の内容があったためです。
"「哲学」とは、自分にとってあまりにも自明で疑う必要のないこと、日常生活で何となく常識として通用していること、みんなの行動や価値観の大前提になっていることについて、本当にそうなのだろうか、そう判断できる根拠はあるのか、なぜ何故そういうことになったのか、といった問いを発し、安易に答えを出すことなく、とことん考えようとする営みである。"
これは哲学史全般に言えることですが、哲学者には決まった答えがあるわけではなく、彼らはそれまでの哲学者が打ち立てた論考を否定して自身の哲学を語ります。だから言ってしまえば上の文章にあるように正しい答えは存在しないのです。
科学で限界に達し問題を解決できないから哲学に任せたいと言っても、哲学もまた明確に答えられるわけではなく、だからこそ今までの学問では私たちはこの先には進めないと言ってもいいと思います。
一応、ハイデガー語った内容で気になったところを少しだけピックアップします。
彼の哲学では"存在者"と"存在"の関係性を追求する姿勢が基盤にあり、存在への問いを問う存在者を現存在として、それを中心に論理展開しています。存在者とは私たち人間を含む身の回りにあるあらゆるものであり、存在とはその存在者を生む暗がりのようなもの、そして現存在は私たちのような人間だと言えます。
私たち一般人が思う存在(存在者)よりもさらに普遍的な概念(存在)を導入したことはとても印象深く、令和哲学の観点からもかなり核心を突いたシャープな論理だと思います。
また彼は道具連関という言葉を使って、この世界は全てが関連しあっているため現存在(人間)はそこから独立しえないとも言っています。これも時間を入れた4次元世界の中でしか存在できない人間のことを語っていると見ることができ、ここでも鋭い洞察をしていると言えるでしょう。
このように令和哲学から見るととても面白く理解できるのですが、先にも言ったようにあくまで哲学には答えがなく、科学を補完するには及びません。
一方令和哲学は哲学とはいうものの、科学や宗教、哲学などあらゆる知を統合できるスーパーサイエンスであり、ファイナルアンサーを有しています。
令和哲学者 NohJesu は「世界の限界は理解の限界、理解の限界は言語の限界」と言います。
人間は科学によって宇宙自然に対する理解を深め、科学が生まれる前に比べると飛躍的に自らの可能性を広げることに成功しました。しかしシンギュラリティを目前にした今、科学による理解では不十分でありさらなる理解を私たちは求められているのです。
現在の理解の限界を越えるためには、NohJesu のいうとおり言語の限界を突破することです。それは今まで私たち人間が使ってきた暗記言語ではなく、真理の活用応用を可能にするイメージ言語を習得すること。それは令和哲学のファイナルアンサーにつながる世界なのです。
本日も最後まで読んでくださりありがとうございました。